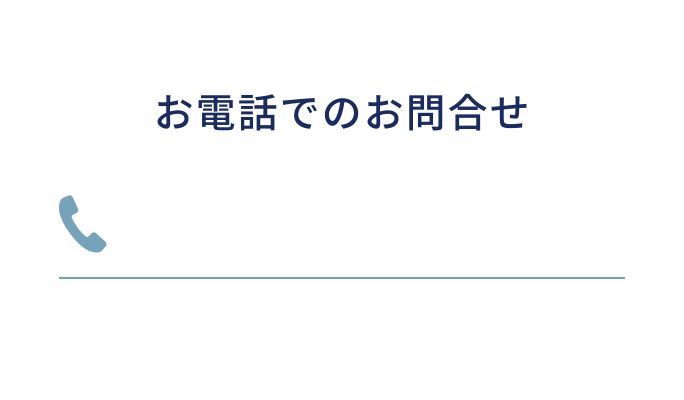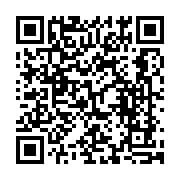香港の弁護士の費用相場や対応可能な分野
目次
香港の法制度と弁護士について知る

香港は一国二制度のもと、中国内の特別行政区となっていますが、中国本土とは全く別の法律や司法制度が適用されます。香港の法律は英米法をベースにしており、判事には英国留学経験者や英国法曹資格保有者が多数います。また、香港の実社会は欧米類似の契約社会となっています。トラブルを未然に防ぐためにも重要な取引では、署名をしてしまう前に弁護士への契約書作成や契約書内容のレビューを依頼することが一般的です。
香港の弁護士は、ソリシター(事務弁護士)とバリスター(法廷弁護士)の2種類に分かれます。ソリシター(事務弁護士)とは、依頼者への法的アドバイス、各種契約書の作成、書類の署名認証、企業のM&Aなどの法的サポート、離婚協議、法廷外の訴訟活動などの事務的対応を主におこなう弁護士です。バリスター(法廷弁護士)とは、訴訟や仲裁において依頼者の法廷弁論が必要となった際に、依頼者からソリシターを通じて委任を受けて法廷や仲裁廷での対応をおこなう弁護士となります。通常のソリシターは、裁判所での弁論権を持ちませんが、「Solicitor Advocates」という資格を持つ一部のソリシターは高等法院(第一審裁判所、高等裁判所)と終審法院(最高裁判所)での弁論権を持ちます。弁護士の費用相場やご案内までの流れ
香港の弁護士の費用相場や対応の流れについてご案内します。当社では相談者の状況や要望に応じて専門分野に長けた弁護士や日本語の話せる優秀な弁護士をご案内しています。
| 当社サポート費用 | 相談無料
※相談内容に合わせて弁護士をアレンジします。ご要望に沿った弁護士におつなぎするまでのサポート事務手数料として500香港ドルを頂戴します。必要な場合、別途費用で翻訳や通訳などのサポートもおこないます。 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 弁護士より直接請求 |
| 対応分野 | 企業法務 (契約書作成、債権回収、労務問題、知的財産、M&A・組織再編など) / 香港にある資産の相続 / 税務相談 / 離婚や財産分与 / 越境ECのトラブル / 不動産取引やトラブル / 各種ライセンス取得 / 消費者被害 / 詐欺被害 / 交通事故 / 金銭問題 / 刑事事件 / 誹謗中傷 / 書類の認証 / その他トラブル |
香港の弁護士の費用相場
弁護士をご案内するまでの流れ
弁護士をご案内するまでの基本的な流れをご案内します。当社では相談者のニーズに合わせて最適な弁護士をご案内しており、ご相談は電話やLINE、SkypeやZoomなどでも受けています。
- メールやお電話などで弁護士についてのお問い合わせをいただきます。
- 当社のアドバイザーが相談者の状況や要望をお伺いします。
- 相談内容に応じられる弁護士を選定してご案内します。
- ご要望に沿った弁護士が見つかりましたら直接相談をしてください。
香港の裁判制度と裁判所について

香港の裁判所は日本と同様に三審制となっています。例えば、区域法院(District Court)や原訟法庭(Court of First Instance)での一審判決に不服があれば、上級の上訴法庭(Court of Appeal)に控訴することになります。なお、原訟法庭と上訴法庭を併せて高等法院(High Court)と言います。さらに上訴法庭の判決に不服があれば、上訴の許可を上訴法庭もしくは終審法院から得て最上級の終審法院(Court of Final Appeal)に上訴をおこなうことができます。なお、香港基本法の解釈等に関わる一定の事件については、香港終審法院の判決は中国の全人代常任委員会による再審査の対象となります。
香港の主な裁判所は以下のとおり
- 終審法院(Court of Final Appeal):
- 上訴法庭からの控訴事件。最終審裁判機関
- 上訴法庭(Court of Appeal):
- 原訟法庭及び区域法院からの控訴事件
- 原訟法庭(Court of First Instance):
- 民事事件(訴訟額の上限なし)及び一定の深刻な罪名の刑事事件
- 区域法院(District Court):
- 訴訟額が300万香港ドル以下の民事事件、及び一定の罪名の刑事事件
- 裁判法院(Magistrates’ Court):
- 重大な刑事事件以外の、軽微な刑事事件の一審など
- 少額審判所(Small Claims Tribunal):
- 訴訟額が7万5000香港ドル以下の民事事件
その他の裁判所は以下のとおり
- 労資審判所(Labour Tribunal):
- 給与の未払い、解雇時の退職金トラブルなどの労務問題
- 家事法庭(Family Court):
- 離婚および離婚に関連する事項(財産分与、養育費等)
- 土地審判所(Lands Tribunal):
- 建物管理の争議、土地回収の賠償争議、家賃未払い等の土地や不動産問題
良く寄せられる相談内容
従業員との労務問題が発生した場合

主に賃金トラブルが原因となり、香港では従業員が労工処(Labour Department)の労資関係課(Labour Relations Division)に駆け込むことが多くあります。従業員が労工処に駆け込むと労工処職員が仲介役となり問題に対する調停がおこなわれます。和解に至らない場合は労働審判所へと移行します。
給与や残業代の未払い、業務内容の誤認識、解雇などにより起こる労務問題を回避するためにも、雇用主は雇用条例をしっかり理解した上で雇用契約書を作成して従業員と締結してください。香港の雇用条例に詳しくない場合は作成した契約書のレビューを弁護士に依頼すると良いでしょう。香港の法律に則った契約書の作成依頼
 香港は契約社会であるため進出企業や新規ビジネスを立ち上げたばかりの企業は、トラブル防止のためにも法令に則った契約書を準備しておくことが重要です。基本となる契約書には、売買契約、ローン契約、フランチャイズ契約、ライセンス契約、業務委託契約、株式譲渡契約や株主間契約などM&Aに関する契約、雇用契約などがあります。香港で有効な契約書の作成をご希望の場合はお気軽にご相談ください。
香港は契約社会であるため進出企業や新規ビジネスを立ち上げたばかりの企業は、トラブル防止のためにも法令に則った契約書を準備しておくことが重要です。基本となる契約書には、売買契約、ローン契約、フランチャイズ契約、ライセンス契約、業務委託契約、株式譲渡契約や株主間契約などM&Aに関する契約、雇用契約などがあります。香港で有効な契約書の作成をご希望の場合はお気軽にご相談ください。
離婚の条件と財産分与や慰謝料について

夫婦のどちらかもしくは両方が香港で居住している場合、香港で離婚の裁判を起こすことができます。香港で離婚する場合、日本のような協議離婚は認められておらず離婚裁判をおこなう必要があります。裁判では離婚を認めるための以下の要件のいずれかを満たしていることを示す必要があります。
- 配偶者が不倫しており、共同生活が耐えられない。
- 配偶者の非合理的な行為に共同生活が耐えられない。
- 離婚申請前に、少なくとも連続1年以上、配偶者が責務を放棄している。
- 離婚申請前に、少なくとも1年以上別居しており、互いに離婚に同意している。
- 離婚申請前に、少なくとも2年以上別居している。
投資詐欺や債権回収についての相談

投資詐欺は加害者の所在が分からないことが多く詐欺の立証ができないことがほとんどです。投資先企業が事業や投資で失敗をして返済能力がない場合においても被害額の回収が難しいといえます。裁判で勝てる場合でも弁護士費用などが掛かりますので被害額を回収できるかを想定して対応していくことが大切です。
債権回収については、取引先などに催促をしても期限どおりに代金などを支払ってくれない場合、弁護士に債権回収の依頼をして裁判を起こすことにより解決につながることがあります。裁判を起こして判決を取得することにより、債務者側の財産について強制執行をしたり、債務者について破産申立をすることができます。親族が香港に資産を残して亡くなった場合

親族が香港に資産(預金・株式・不動産など)を残して亡くなった場合、弁護士による遺産相続手続(プロベート)が必要となります。プロベートとは、「人格代表者」と呼ばれる遺産管理人又は遺言執行者が死亡証明書、除籍謄本、(もしあれば)遺言書(及びこれらの英訳)、日本法弁護士意見書、財産・債務等の一覧表など」を高等法院の遺産承弁処(The Probate Registry)に提出して裁判所の遺産管理状(Grant of Letter of Administration)又は遺言検認所(Grant of Probate)を得る手続きのことを言います。この裁判所の遺産管理状又は遺言検認書を得てからでなければ、相続財産の回収・分与おこなうことができません。香港の銀行口座、保険契約、証券口座、不動産や非上場株式、債権債務については、このプロベートが終わるまでは現金化することができません。日本人が香港でプロベートをする場合は、国際私法が関わるため原則として香港弁護士(ソリシター)による代理が必要です。一般的にプロベート完了までの費用は15万香港ドル以上、期間は1年前後となります。
香港に相続税はありませんが遺産分配でのトラブルが頻繁に発生しているため、遺産相続でトラブルとならないように弁護士を通じて予め遺言書を作成したり、財産関係の書類や必要情報を整理しておくことが重要です。香港の不動産取引に関する対応について
 香港の不動産売買、賃貸、仲介、管理、開発などの契約書作成や関係者との交渉、政府関係の手続きなどが必要な方は弁護士を通じてサポートすることができます。香港以外に住んでいる方で香港に来ることが難しい場合は、香港の弁護士が代理人となり不動産取引をおこなうこともできます。不動産取引は大きな金額が動くため、トラブルとならないように慎重な対応が必要です。不動産賃貸については、日本の借地借家法のような借主を保護する法律がありませんので、事務所物件や住宅を賃貸する場合、契約内容を事前に弁護士にレビューしてもらうことをお勧めします。不動産売買については、日本と異なり司法書士ではなく、弁護士(ソリシター)を売主買主がそれぞれ代理につけて、権利書や登記関係書類をチェックしながら売買取引を完了します。
香港の不動産売買、賃貸、仲介、管理、開発などの契約書作成や関係者との交渉、政府関係の手続きなどが必要な方は弁護士を通じてサポートすることができます。香港以外に住んでいる方で香港に来ることが難しい場合は、香港の弁護士が代理人となり不動産取引をおこなうこともできます。不動産取引は大きな金額が動くため、トラブルとならないように慎重な対応が必要です。不動産賃貸については、日本の借地借家法のような借主を保護する法律がありませんので、事務所物件や住宅を賃貸する場合、契約内容を事前に弁護士にレビューしてもらうことをお勧めします。不動産売買については、日本と異なり司法書士ではなく、弁護士(ソリシター)を売主買主がそれぞれ代理につけて、権利書や登記関係書類をチェックしながら売買取引を完了します。
香港居住と税務(日本・香港)にまつわる相談
 香港(海外)と日本の両方でビジネスをしている方から個人所得税の納税義務や課税範囲についての相談を多く受けます。日本の税法上は日本居住者か非居住者かの判定によって納税義務が決められます。そのため、香港でビジネスをおこなっている場合でも日本から日本居住者だと認定されると日本の高い個人所得税の対象となる可能性がありますので、香港や海外でビジネス活動をしている方は、日本の基本的な税法や居住地判定について理解しておくことが重要です。香港では60日超香港に滞在して、香港源泉所得がある個人は香港で個人所得税を申告・納税する義務があります。出張ベースで働いたり、香港の法人から給与を受け取っている場合、香港での納税義務があるのか、無いのかについて、しっかりと専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
香港(海外)と日本の両方でビジネスをしている方から個人所得税の納税義務や課税範囲についての相談を多く受けます。日本の税法上は日本居住者か非居住者かの判定によって納税義務が決められます。そのため、香港でビジネスをおこなっている場合でも日本から日本居住者だと認定されると日本の高い個人所得税の対象となる可能性がありますので、香港や海外でビジネス活動をしている方は、日本の基本的な税法や居住地判定について理解しておくことが重要です。香港では60日超香港に滞在して、香港源泉所得がある個人は香港で個人所得税を申告・納税する義務があります。出張ベースで働いたり、香港の法人から給与を受け取っている場合、香港での納税義務があるのか、無いのかについて、しっかりと専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
香港に向けた越境ECに関連する相談
 中国から香港、日本から香港など、インターネットを活用して香港外から香港に商品を販売する越境ECでは、電子商取引に関連する法律や、各種商品・サービスに関する香港現地の法規制への理解が必要です。越境ECには、不正カード利用、損害賠償、商品の破損や不着、現地法律違反など様々なトラブルがつきものです。さらにトラブル発生時にはどちらの国で裁判をおこなうかなど複雑な要素が加わります。これらの予防のため、香港向けに越境ECをする場合は、弁護士の支援を受けて現地法規制の調査や香港法に則した利用規約・個人情報保護方針の作成をすることをお勧めします。お困りのことがございましたら、当社にお気軽にご相談ください。
中国から香港、日本から香港など、インターネットを活用して香港外から香港に商品を販売する越境ECでは、電子商取引に関連する法律や、各種商品・サービスに関する香港現地の法規制への理解が必要です。越境ECには、不正カード利用、損害賠償、商品の破損や不着、現地法律違反など様々なトラブルがつきものです。さらにトラブル発生時にはどちらの国で裁判をおこなうかなど複雑な要素が加わります。これらの予防のため、香港向けに越境ECをする場合は、弁護士の支援を受けて現地法規制の調査や香港法に則した利用規約・個人情報保護方針の作成をすることをお勧めします。お困りのことがございましたら、当社にお気軽にご相談ください。
香港における各種営業規制や許認可
 香港でビジネスをおこなうには各種営業規制を理解し、必要な場合はライセンスを取得することが重要です。例えば、レストランやバーではレストランライセンスやリカーライセンスを取得しなければなりません。不動産仲介、証券売買、人材紹介、医薬品の販売など、他にもライセンスが必要な業種がありますので、ビジネスの立ち上げに合わせてライセンスの必要有無を確認する必要があります。
香港でビジネスをおこなうには各種営業規制を理解し、必要な場合はライセンスを取得することが重要です。例えば、レストランやバーではレストランライセンスやリカーライセンスを取得しなければなりません。不動産仲介、証券売買、人材紹介、医薬品の販売など、他にもライセンスが必要な業種がありますので、ビジネスの立ち上げに合わせてライセンスの必要有無を確認する必要があります。